クマはもっぱら噛みつき、爪で引き裂いた。両者の体が離れると、クマはバイソンに打撃をくわえ、再び噛みついた。午後1時過ぎに始まった戦いは何度もインターバルをとって続き、終わったのは午後6時頃だった。
クマが(おそらく疲労から)引き揚げてしまった時、バイソンはまだ生きていた。Wyman が確認のため近づいた時、バイソンは一度歩きかけたがすぐに倒れ、二度と起きあがらなかった。


O・ブレランド(1948)はカリフォルニアでハイイログマとバイソンの戦いがおこなわれたと書いている。そしてたいていはクマが勝っていると。ある時などは続けて4頭のバイソンと戦いこれを倒したクマもあったという。
|
アーネスト・シートン(1925)もバイソンとハイイログマが戦うぞくぞくするような話をたくさん耳にしてきた。バイソンが勝ったことも、クマが勝ったこともあった。中でも悲惨な話は、何ラウンドも戦った末、ついにバイソンがよろめき倒れ、同時にクマも角で腹を引き裂かれて死にかけているという展開だった。しかしシートンはこれらの話が事実であると証明することはできなかった。 シートンによればクマが雌のバイソンを襲った時、すぐに雄のバイソンが救援に駆けつけた。バイソンはクマを角で空中に突き上げ、落下してきたところをさらに突いて殺してしまった。シートンは単にクマとしか書いていないしクマの大きさにも触れていないのでハイイログマかどうかはわからないが。 |
イエローストーンでハイイログマの死体が見つかったことがある。クマはあちこちが打撲で血だらけになっており、左胸には直径4cmほどの穴があいていた。死骸の周りには激しく争った痕跡が認められ、バイソンの足跡も多数みつかった(Yellowstone Bear Tales, 1991)。 ダコタのベテランハンターは、大きな雄のハイイログマがバイソンの群に近づくところを目撃した(The Great Buffalo Hunt, 1959)。数頭の雄が雌と子を守るためにクマに立ちはだかった。 クマは1頭の雄を前足で激しく打ち据え、背骨を砕いてあっさりと殺したが、他のバイソンは角で突きかかってクマに深手を与えた。クマはほとんど這うようにしてその場を逃れた。 |
ハイイログマは雑食性だが機会さえあれば肉食をする。イエローストーン公園のハイイログマは、他の地域のものに較べ肉食の比率がかなり高いといわれる。80年代から90年代にかけてのイエローストーンでの調査では、雄のハイイログマは必要なエネルギーの50%以上を肉から得ていることがわかった。その多くは冬の間に死んだ動物の死骸や、オオカミが殺したシカなどだったが、まれには自らの手でワピチやムーズを殺したこともあった(Wyman, 2002)。
|
ハイイログマが成獣のバイソンを襲った話は非常に少ない。Travis Wyman(2002)は20世紀後半に著された野外研究をいくつも調べたがその実例をほとんど見つけられなかった。彼自身は2000年9月に、イエローストーンで雌のハイイログマがまだ若い雄のバイソンを攻撃するところを目撃している。それは前足の一撃で殺すという単純なものではなかった。 クマはもっぱら噛みつき、爪で引き裂いた。両者の体が離れると、クマはバイソンに打撃をくわえ、再び噛みついた。午後1時過ぎに始まった戦いは何度もインターバルをとって続き、終わったのは午後6時頃だった。 クマが(おそらく疲労から)引き揚げてしまった時、バイソンはまだ生きていた。Wyman が確認のため近づいた時、バイソンは一度歩きかけたがすぐに倒れ、二度と起きあがらなかった。 |
 |
ハイイログマはよく牧場を襲いウシを殺したが、ウシがいつも容易に殺されていたわけではない。中には敢然とクマに挑み、引き裂いた肉と血を角に引っかけて凱旋してくる強者もいた(Bancroft, 1886)。
 ↑1849年、カリフォルニアの牧場近くで起こったウシとグリズリーの戦い。激戦の末にウシはクマの腹を突き破ってとどめを刺した。しかしその場を立ち去りかけて倒れ、ウシも死んだ(J. Browne, 1862)。
↑1849年、カリフォルニアの牧場近くで起こったウシとグリズリーの戦い。激戦の末にウシはクマの腹を突き破ってとどめを刺した。しかしその場を立ち去りかけて倒れ、ウシも死んだ(J. Browne, 1862)。 |
西部開拓時代、19世紀にメキシコ領カリフォルニアの闘技場に登場したのはバイソンではなく、血気盛んなウシだった。それも今日の牧場で見られる肉牛のヘレフォードなどではなく、太くてしなやかな首、鋭い角、軽やかなフットワーク、そして常に戦闘準備にあって、カタパルトから打ち出されたように攻撃する Spanish Bull だったと Homer Kingsley(1920)は書いている。 |
土地測量の一行が、アラスカの Geographic 湾近くでウマを上陸させようとしていた時、天候が急変して暴風が吹き、艀に乗せられていたウマは荒れ狂う海に投げ出された。そして1頭だけがなんとか岸まで泳ぎ着くことができた。
それから数ヶ月、海岸では1頭の雄ウマがしばしば目撃されていた。漁船が時折立ち寄って人なつっこいウマに餌を与えたりしていた。これはウマにとって少なからぬ助けとなっていたようで、それから3年後には精悍なウマは近辺の名物になっていた。ヒグマの多い地であったにもかかわらず。
ある日、ハンターの Bill Kvasnikoff は船で岸の近くを通りかかった時、2頭のヒグマがウマの後を追っているのを見つけた。船のエンジン音を聞いて岸に駆けつけたウマは何か差し入れがあるかと海岸に立ち止まっていた。
追いついた2頭のクマはウマを打ちつけ、噛み砕き、引き裂こうとした…が、彼らを迎え撃ったのは強烈な蹴りであり、彼らのそれに劣らぬ噛みつきであった。さらにウマは円を描いてめまぐるしく動き、クマの膝を何度も攻め、そのバランスを崩した。ウマの蹴りが跳ぶとクマの毛が、皮膚が飛び散った。砂塵が両者の周囲に舞い上がり、その中から暴れウマの雄叫びとクマの咆吼が聞かれた。
戦いは5分ほどで終わった。クマは自らの安全を求め、猛り立ったウマの追撃を免れるために全力で走り去った。
こうした出来事は過去3年の間に何度もあったと推察される。そのたびにウマは野に生きる経験を重ねていたのだ(Gerald L. Wood, 1977)。
2頭のヒグマが一緒にいるということは繁殖期だったのか、あるいは若いクマだったのかもしれない。原文では two large brown bears とあるが亜成獣のヒグマでも人の目には大きく見えるだろう。
ウマはもっと手強い? ハイイログマが家畜のウシを襲うことはしばしばだが、ウマは意外と少ない。Ben East(Bears, 1977)は子ウマがクマの犠牲になることはあるが、おとなのウマはグリズリーとって "Too hard"、手にあまる相手だという。これはウマの足が速くてとても捕まえられないという意味だろうか? シートン(1925)は、ニューメキシコのカウボーイから、ハイイログマが一撃でウマを倒すところを見たことがあると聞かされた。 一方、ルーズベルトはハイイログマに襲われた雄のウマが、果敢に反撃してその顎を蹴り砕き、追い払ったという。 またイエローストーンで、M. K. Skinner は彼が飼っていたウマが(クマの方から襲ってきたのではなく)クマを攻撃したことを語っている。近くでクマを眼にしたウマは、すぐさまダッシュをかけ、何度も蹴りつけ、目的を遂げるとさっさと引き揚げてきた。このウマは2度クロクマを殺し、数回ハイイログマを追い払ったという(Gary Brown, Great Bear Almanac, 1993)。 |
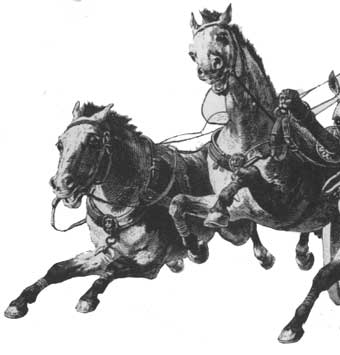 |
北海道では1904〜1928年に年間100頭以上のウマがヒグマに殺されている。最も被害が多かった1910年に殺されたウマは338頭にのぼる。その後農耕馬自体が減少したため、殺されたウマの数も激減している(木村盛武,2001)。
囲いの中ではウマが何頭も殺されることがある。1890年4月に石狩の桑田牧場をクマが襲った時には6頭のウマを殺し、7頭目をさらっていった。日中放牧されているウマはすぐに逃げることができる。1906年頃、十勝の晩成社牧場でヒグマが種ウマを襲った時には逆に激しい反撃を受け、頭を蹴られたクマは血を吐いて悶絶した(木村盛武,1995)。