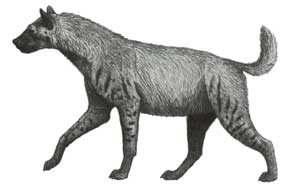6歳の女の子がベランダで寝ていた。アフリカ南部・マラウイの夏、室内は耐え難いほどに暑かった。1頭のブチハイエナが近くの茂みからそっと這い出してきて、ベランダに侵入すると、幼い子の命を噛み砕いた。すぐに他のハイエナたちも飛び込んできて、すでに息のない体に群がった。物音に気づいた両親が何とかハイエナを追い払ったが余りにも遅すぎた(G. W. Frame, 1976)。
マラウイではブチハイエナが人を襲った例が多く報告されている。1955年に起こった死亡事故3件がその始まりだった。就寝中の大人、子供が小屋から引きずり出され、食べ尽くされた。その後の5年間で27人(多くが子供)がハイエナに食べられた。
被害者の多くが同じような状況で襲われている。現地では暑くて乾燥した時期になるとベランダで寝るようになる。ハイエナは眠っている人を掴んでベランダから運び出し、茂みの中で食べたのだった。マラウイではこの事例と同じようにハイエナが人の捕食に執着する時期が、過去にも幾度かあったという。
ケニヤでは、ラクダの番をしていた少女が昼寝をしていたところ、腹を空かせたハイエナが彼女の顔から肉をもぎ取った。少女の悲鳴で駆けつけた人々によって彼女は救われた。
1995年にはセレンゲティ近くで、アメリカ人の旅行者がテントから引きずり出され、顔と手を咬まれた。マサイ人のガイドが槍でハイエナを攻撃して救出した(H. Kruuk, 2002)。
またあるアフリカ人はブチハイエナの一噛みで、鼻と歯、舌、そして下顎の大半を失った。彼もまた、暑い夜に家の外で寝ていて、ハイエナに咬まれたのだった。それでも彼は命は助かったがはたして運が良かったというべきか。(Frame, 1976)。
 |
|
従来ハイエナはいろいろと悪くいわれてきた。主な理由の一つは、そのスタイルのせいだろう。体の後半部が肩よりも下がっていて、何かこそこそとした感じを与える。その格好で死体をあさる習性のために蔑まれることになった。またあの甲高い奇妙な声もマイナスだっただろう。
ハイエナというとスカベンジャーの代表のように思われているが、地域によっては意外なほど自分たちで狩りをする。セレンゲティにおけるハンス・クルーク(1972)の調査では、ハイエナが食べていたヌー(成獣)136頭の内、85頭が自分たちで捕らえたものだった。夜や曇った日に群で狩をおこなうのが普通だが、時には単独でも、また2、3頭でも獲物を探す。大きな群の方が成功率が高いし、またより大きな草食獣を捕らえることができる。クルークによれば、単独の狩21例中で成功したのは4回だけだったが、群による狩ではほとんど全て成功しているという。
|
セレンゲティやンゴロンゴロではブチハイエナの獲物の3分の2はヌー(ウシカモシカ)である。ハイエナはライオンに獲物を奪われることが少なくない。
ハイエナの群はあの有名な笑い声で吼えながら、捕らえた獲物を手早く片づける。ライオンはその騒ぎに引き寄せられることがたびたびあって、その耳障りな声の録音を聞かせると、それに誘われてやってくることさえある(バートラム、1978)。
ンゴロンゴロではライオンがブチハイエナにたかることが多い。しかし争奪戦は単純ではない。ブチハイエナが捕らえた獲物をライオンが横取りして食べ始めても、ハイエナが諦めず、やがて攻め返して、食べているライオンを追い払うのだ。一晩で獲物の所有者が何度も交代することさえある。
ハイエナが狩に成功すると、そこへ他のハイエナも集まるので、ライオンがやってくる前にあらかた食べ終えていることも少なからずあるだろう。38頭のハイエナがシマウマをしとめた時には、15分で死体を片づけてしまった(Macdonald, 1984)。
 |
|
ブチハイエナは肩高70−90cmでヨーロッパオオカミと同じくらいだが、体重ではかなり勝る。
タンザニアのンゴロンゴロ火口原で計量された3頭はいずれも50kgだった(Frame, 1976)。ボツワナ産の2頭は73kgと79kgだった(Smithers,1971)。クルーガー産の大きな雌は88kgあった(Smuts, 1982)。
16頭のブチハイエナが2頭のアフリカゾウを取り囲んでいたことがある。攻撃はしなかったがゾウは困惑していたという(小原、1968)。
←ブチハイエナの群はカバをも狼狽させる。
※ マリモさんから教えていただきました。 |

現在、アフリカやアジアを徘徊しているハイエナは僅かに4種だけだが、このグループ(ハイエナ科)には70種を数える絶滅種が確認されている。最初の典型的なハイエナが出現したのは第三紀中新世、1700万年も前のことである。
全時代を通じて最も注目すべきハイエナは、カスマポルテテスやユーリボアーズ Euryboas だ。これらのハイエナはアフリカからユーラシア、さらには北アメリカへと広がった。新世界へ進出した唯一のハイエナだろう。基本的な特徴は明らかにハイエナであるが、四肢が長く、この四肢とさらに歯までもがチーターに驚くほどよく似ていて、走行性の捕食者に進化していた。旧世界の鮮新世後期から更新世中期にかけて(50−350万年前)大型種のチーター Acinonyx(肩高90cm)も存在し、おそらく激しく競合しただろう(クルテン、1976)。
現在の3種のハイエナは骨まで食べ尽くす骨砕き型だが、鮮新世には走るのが速く、追いかけて狩りをするタイプのハイエナが栄えていた。
南アフリカのランゲバーンウェグの遺跡から見つかったカスマポルテテス(→)Chasmaporthetes australis は現在のブチハイエナよりも背が高く(肩高88cm)、体の作りは軽快で、頭は相対的に小さかった。後脚は前脚に比べてそれほど短くはなく、つまり現在のハイエナほど背は傾斜していなかった。その歯も骨砕き型ではなく、肉や皮を噛む方に適応している。これらの特徴は、もっと活動的な捕食者のイメージを彷彿させるものである(アラン・ターナー、2004)。 |
|
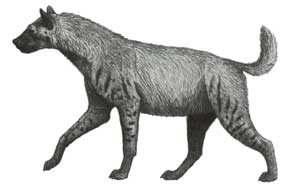 |
最大のハイエナ Giant Short-faced Hyena パキクロクタ Pachycrocuta brevirostris は鮮新世後期(350万年前)に東と南のアフリカに現れた。更新世前期にはユーラシアに広まっていた。肩高1m、体長1.8m、推定体重は120−150kgに達した。雌ライオンほどもあったわけだ。
パキクロクタの化石がエチオピアのハダールで発掘されている。350万年前にオーストラロピテクスが生きていた頃だ。ケニヤ北部・サウスタークウェルのヒト化石発掘現場でも、大きなハイエナの化石が発見された(ハート&サスマン、2005)。
周口店で見つかったパキクロクタの骨格→ |
|
 |

洞穴で休息する巨大ハイエナパキクロクタとその前を走り去るドール(Alan Turner, 1997)
1920年代に北京南方の周口店洞窟で見つかった北京原人は、人肉嗜好だったとの説がある。特にヒトの脳を食べるという野蛮な習わしがあったというのだ。周口店で多数の人の頭骨が発見され、しかも一様に手が加えられていた。顔の骨は取り去られ、頭骨の一番下の開口部が割り広げられていたのだ。人の頭骨をここまで打ち砕けるのは石器を使ったヒトだけだというのだ。
 |
|
周口店で見つかったヒトの遺体のほとんどは頭蓋骨である。体の骨は少ない。頭蓋骨は他の場所から持ち帰られたものなのだ。北京原人研究の第一人者であるフランソワ・ワイデンライヒは北京原人を、首狩りをした人食い人種だったと見ている。この説に反対する学者はほとんどいない。頭蓋骨の一部が削り取られている。それは大後頭孔の周囲で、脊髄が脳に繋がるところだ。彼らは頭蓋骨に穴をあけて脳を取りだしたのである(R. アードレイ、1976)。
しかし現在のハイエナが周口店化石に見られたのとまったく同じ方法で獲物の頭を食べていることから、北京原人の頭から顔面を剥ぎ取って頭骨の下部を広げ、脳を食べたのはパキクロクタだったことが明白だという。アメリカのノエル・ボアズとラッセル・ショホーンは、周口店のホモ・エレクトスの頭骨には、大型のハイエナが咬んで、砕いた形跡が残っていることを示した。
ハイエナはまず、可食部の顔面筋を剥ぎながら頬骨と上顎を傷つける。続いて上顎の真ん中にひびを入れて舌を届きやすくする。さらに顔面の骨を砕いて骨髄を得る。そして頭蓋冠をこじ開けて脳を貪る。
←パキクロクタは洞窟の周辺で獲物を襲い、持ち帰った。パキクロクタの口は、ほぼ完全に人間の頭を包み込めるほど大きいのだ(uiowa.edu)。 |